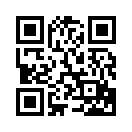マングースの目撃情報や、活動に関するお問い合わせは下記の連絡先にお願いいたします。
<一般財団法人自然環境研究センター 浦上事務所 鹿児島県奄美市名瀬浦上1385-2
TEL:0997-58-4013
環境省奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551TEL:0997-55-8620
このブログの写真の無断転載はご遠慮ください。写真については、一部を除いてメンバーが休日等利用して撮影したものを使用しています。2019年03月14日
茶色いまだら模様の卵はアマミヤマシギ
みなさんこんにちは!
先日作業中にアマミヤマシギの卵を見つけました。
奄美マングースバスターズでは毎年作業中に見つけたアマミヤマシギの巣を記録しています。
この巣で今年に入って3件目の発見です。暖冬の影響か例年に比べ早い傾向にあります。
アマミヤマシギはご覧のように地面に落ち葉をすり鉢状に敷き、その上に2~4個の卵を産みます。
卵の大きさはニワトリの卵より小さく、長径5cm程です。色は茶色でまだら模様があります。通常3週間ほどで孵化します。雛は孵化後すぐ歩けるようになり、30分もすると親鳥は雛を連れて巣を立ち去ります。
こんな無防備な状態ですから外敵からの捕食による脅威にさらされていることは言うまでもありません。もちろんその外敵の中にマングースも含まれます。
アマミヤマシギは奄美沖縄の固有種 で国内希少野生動植物種に指定されている希少な鳥です。しかし、ここ数年今までに確認のなかった場所で巣が確認され、アマミヤマシギの生息域は確実に広がりを見せています。それを、私達マングースバスターズは奄美の自然が回復している確かな手応えと感じています。
今年はヤツガシラやウスバキトンボもすでに確認されており、季節が少し早いように感じます。
餌が豊富で栄養を蓄えることが出来れば、アマミヤマシギの産卵の機会も増えると見込んでいます。
今年はまだまだ多くのアマミヤマシギの巣が見つけられるのではないかと、期待しています。

2018年07月28日
ヤイロチョウ再び
奄美大島では通常、梅雨入りは5月の上旬、7月上旬に梅雨明けです。ジメジメした毎日が続いている奄美大島ですが、ちょっとしたうれしい出来事がありました。
マングースバスターズが、在来種とマングースのモニタリングのために設置しているセンサーカメラに、ヤイロチョウという鳥が再び撮影されました。
ヤイロチョウについては、奄美大島を渡り途中に通過はしているはずですが、姿が確認されず、長らく公式な記録がありませんでした。しかし、3年前にマングースバスターズの設置しているセンサーカメラで初めて撮影され、奄美野生生物保護センターの水田拓さんが「山階鳥類学雑誌」の「報告」に寄稿し、初めて公式に生息が確認されました。
ヤイロチョウ過去記事↓
今回は前回と違う場所で撮影されましたが、どちらも伐採等が長期間行われていない老齢林で、環境は似ています。撮影された時期は前回が5月中旬で、今回は5月下旬でした。



ヤイロチョウは全部で4枚撮影されていたのですが、4枚とも同じ日の撮影で、1枚目が10:00頃の撮影、4枚目が15:00頃の撮影でした。このヤイロチョウは、少なくとも1日は撮影された森の中にいただろうと想像できます。ヤイロチョウを奄美大島で目にすることがなかった原因として、島が大きくて森が深い、ということがあるかもしれませんが、島にいる期間が短いということもあるのではないかと思います。
こんなにカラフルなので、山の中でも目立つのかなと思いますが、人の気配を感じると忍者のように地面を歩いて姿を隠すので 意外と目立たないそうです。まさに幻の鳥ヤイロチョウ。奄美の森で見てみたいです。
梅雨時期の楽しみとして、来年の5月中旬から下旬には、ヤイロチョウに注意して山の中を歩いてみたいです。
マングースバスターズが、在来種とマングースのモニタリングのために設置しているセンサーカメラに、ヤイロチョウという鳥が再び撮影されました。
ヤイロチョウについては、奄美大島を渡り途中に通過はしているはずですが、姿が確認されず、長らく公式な記録がありませんでした。しかし、3年前にマングースバスターズの設置しているセンサーカメラで初めて撮影され、奄美野生生物保護センターの水田拓さんが「山階鳥類学雑誌」の「報告」に寄稿し、初めて公式に生息が確認されました。
ヤイロチョウ過去記事↓
今回は前回と違う場所で撮影されましたが、どちらも伐採等が長期間行われていない老齢林で、環境は似ています。撮影された時期は前回が5月中旬で、今回は5月下旬でした。
ヤイロチョウは全部で4枚撮影されていたのですが、4枚とも同じ日の撮影で、1枚目が10:00頃の撮影、4枚目が15:00頃の撮影でした。このヤイロチョウは、少なくとも1日は撮影された森の中にいただろうと想像できます。ヤイロチョウを奄美大島で目にすることがなかった原因として、島が大きくて森が深い、ということがあるかもしれませんが、島にいる期間が短いということもあるのではないかと思います。
こんなにカラフルなので、山の中でも目立つのかなと思いますが、人の気配を感じると忍者のように地面を歩いて姿を隠すので 意外と目立たないそうです。まさに幻の鳥ヤイロチョウ。奄美の森で見てみたいです。
梅雨時期の楽しみとして、来年の5月中旬から下旬には、ヤイロチョウに注意して山の中を歩いてみたいです。
2015年08月08日
ついにでた! 奄美初記録の鳥
奄美マングースバスターズでは自動撮影カメラによるモニタリング調査を行っています。
自動撮影カメラは、カメラの前を動物が通過すると写真撮影することのできる撮影機器で、これまでにいろいろな動物が撮影されてきました。過去にはアマミノクロウサギの交尾や、 アマミトゲネズミ、ケナガネズミ の貴重な生態写真を撮影したこともありました。

また、アマミノクロウサギのモニタリング用に環境省が設置した自動撮影カメラには、ノネコがアマミノクロウサギを咥えた写真のようにインパクトの強い写真が撮影されることもありました。
今回、ピンポイントチームがマングースの目撃情報をもとに設置したカメラに見たことのない鳥が写っているので種同定を依頼されました。
渡りの時期なので何が写っているのかなと思いながらプリントアウトした写真を見て思わず椅子から転げ落ちてしまいました。
というのは大げさですが、漫画などで驚いたときに椅子から「ガタッ」とずり落ちたりするシーンさながらの衝撃でした。
なんと写っていたのはヤイロチョウ!

思わぬところでまだ見ぬ珍鳥との出会いでした。
(後で聞いたところによると、奄美野生生物保護センターの職員もヤイロチョウの情報を伝えたら私と同じようにとてもいいリアクションだったそうです。ヤイロチョウで大げさに驚くリアクションをとるのは鳥屋あるあるのようです)
奄美大島でヤイロチョウの公式な記録はまだ無く、この自動撮影カメラでの撮影が現段階で奄美大島での初めての記録になると思います。
ヤイロチョウは夏鳥として日本に渡ってきますが多くはなく、まだ生態がはっきりわかっていない珍鳥中の珍鳥です。世界にはおよそ30種いますが日本に渡ってくるのは1種だけです。高知県の四万十川流域や、鹿児島県と宮崎県境の霧島連山が繁殖地として有名で、保護活動も行われています。
鳴き声は「ホヘン、ホヘン」という大きな声で鳴き、近くで聞くととてもうるさいようですが、私が聞いたときは雨の中よく通るきれいな声だなと思いました。
以前、岐阜県で声を聞いたことがあったので何度か通いましたが結局姿は見られなかったので、見てみたい鳥の一つになっていました。
ヤイロチョウの名前の由来は、漢字で「八色鳥」と書くように八つの色を持つ鳥、たくさんの色という意味の八色、見る時によって色が違うからというように諸説あります。写真を見ると頭の方から茶色、クリーム色、黒色、背中は緑色、上面にコバルトブルー、尾羽に青色、下尾筒 (尾羽の下部あたり)に赤色、翼を広げると白斑があるので8色なのですが、脚の色のピンク色を入れると9色に…結局は見る人によって色の数も変わるし、細かく色を分けていったら8色以上の多色になってしまいます。日本で記録のあるヤイロチョウの仲間で、ズグロヤイロチョウというのがいますが、写真を見た感じ8色ではないようだし、海外のヤイロチョウの仲間は8色ないものや8色以上のものもいるので、名前の由来はたくさんの色というのがもっともそうですね。
世界には約30種類ほどいて、みな色鮮やかな体色です。興味のある方はネットで検索してみるといろいろなヤイロチョウの画像が見られます。
奄美大島でも渡の時期にはいつかは見られるだろうと思っていましたが、これで確実にヤイロチョウは奄美大島を通過しているということが分かったので5月中旬梅雨時期の楽しみが増えました。次はどんな珍鳥が写るか楽しみです。

2013年07月22日
オオトラツグミの営巣を確認

オオトラツグミの巣です。
作業中に偶然発見しました。

朽ちた枝の付け根にすっぽりと収まっていました。

自動カメラで撮影されたオオトラツグミです。肉眼ではなかなか観察できませんが、名前の由来となっているトラ模様が美しい鳥です。
オオトラツグミは奄美大島のみに生息し、国指定天然記念物であり、環境省のレッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類にランクされています。地上でミミズ等を採餌するため、ノネコやマングースによる捕食が心配されており、マングース駆除により個体数回復が期待されています。

通常深い広葉樹林に生息していますが、発見場所は海に近く若齢の広葉樹林とリュウキュウマツが混生した地域です。あまり良い営巣場所が見つからなかったのか、巣は地上から1mぐらいで頭上が開けた場所にありました。こうした場所は捕食者に見つかりやすく、良い場所とは言えません。
発見から10日ほどして環境省の方が現場を確認したところ、巣は荒らされて放棄されていました。外敵のカラスかノネコに襲われてしまったのでしょう。
オオトラツグミが無事に繁殖できる深い広葉樹林が回復することを願うばかりです。

2013年07月03日
珍鳥ラッシュ
今年の奄美大島は、春の渡りで珍鳥が数多く見られました。
珍鳥という言葉は鳥屋(バードウォッチャー)用語です。明確な定義はありませんが、渡りの時期に通過はしているけど見ることが難しい鳥の事を指すのが普通なようです。分布域が限られる鳥や、生息数が少ない鳥のことを珍鳥とは呼ばないようです。
ですから、ルリカケスやオオトラツグミ、アマミヤマシギは奄美大島および徳之島にしかいない鳥なのですが、珍鳥ではありません。
ヘラシギや、カラフトアオアシシギ、オオトラツグミなどは世界的にも生息数が少ない鳥なので本当の意味で珍鳥なのですが・・・
奄美大島では渡の時期には必ず目にするマミジロタヒバリや、ムネアカタヒバリなどは珍鳥という感覚はないのですが、本土では珍鳥です。
逆に本土では普通の鳥であるトビや、ケリは奄美大島では珍鳥です。

奄美では珍鳥のケリ
今シーズンは僕にとって初めて見る鳥を2種類も見ることが出来てとてもいい春の渡りとなりました。
1種目は、念願のシマノジコを見ることが出来ました。

何度かチャンスはあったものの、見ることが出来ていない鳥だったのでとてもうれしかったです。
しかも集落内を散歩している時に見つけたのでびっくりでした。
奄美野鳥の会の図鑑の記録では1995年の写真だったので奄美での記録は約18年ぶりになるのでしょうか?
2種目は、ヨーロッパビンズイで、ムネアカタヒバリの群れの中に色の薄い個体がいたのでよく見たらヨーロッパビンズイでした。

奄美大島では初記録になるそうです。
今シーズンの春の渡りで、一番の珍鳥と言えばマダラチュウヒのきれいなオスの個体が出たことです。
バードウォッチング雑誌「BIRDER」のトレードマークになっていたのでご存知の方も多いかもしれませんが、白と黒のきれいな鷹の仲間で、これはぜひ見たかった鳥でした。
詳しくはこちらのブログを
http://blog.goo.ne.jp/inpre-anac/e/9dda6d05da5a87e46bf2c6eaa51cba2e
見られた時間ちょうど近くにいたのに見られなかったので、とても悔しかったです。
その他に見られた珍鳥たちを紹介します。

オオチドリ
離島ではおなじみのオオチドリ

アカガシラサギ

コシャクシギ

ヒメコウテンシ
一度に200羽の群れが入っていたのには驚きました。

シロハラホオジロ

ノジコ
全般に、奄美群島では渡り鳥の多い年で、色々な珍鳥に出会えました。鳥屋にとってはとてもいい春の渡りでした。

珍鳥という言葉は鳥屋(バードウォッチャー)用語です。明確な定義はありませんが、渡りの時期に通過はしているけど見ることが難しい鳥の事を指すのが普通なようです。分布域が限られる鳥や、生息数が少ない鳥のことを珍鳥とは呼ばないようです。
ですから、ルリカケスやオオトラツグミ、アマミヤマシギは奄美大島および徳之島にしかいない鳥なのですが、珍鳥ではありません。
ヘラシギや、カラフトアオアシシギ、オオトラツグミなどは世界的にも生息数が少ない鳥なので本当の意味で珍鳥なのですが・・・
奄美大島では渡の時期には必ず目にするマミジロタヒバリや、ムネアカタヒバリなどは珍鳥という感覚はないのですが、本土では珍鳥です。
逆に本土では普通の鳥であるトビや、ケリは奄美大島では珍鳥です。

奄美では珍鳥のケリ
今シーズンは僕にとって初めて見る鳥を2種類も見ることが出来てとてもいい春の渡りとなりました。
1種目は、念願のシマノジコを見ることが出来ました。

何度かチャンスはあったものの、見ることが出来ていない鳥だったのでとてもうれしかったです。
しかも集落内を散歩している時に見つけたのでびっくりでした。
奄美野鳥の会の図鑑の記録では1995年の写真だったので奄美での記録は約18年ぶりになるのでしょうか?
2種目は、ヨーロッパビンズイで、ムネアカタヒバリの群れの中に色の薄い個体がいたのでよく見たらヨーロッパビンズイでした。

奄美大島では初記録になるそうです。
今シーズンの春の渡りで、一番の珍鳥と言えばマダラチュウヒのきれいなオスの個体が出たことです。
バードウォッチング雑誌「BIRDER」のトレードマークになっていたのでご存知の方も多いかもしれませんが、白と黒のきれいな鷹の仲間で、これはぜひ見たかった鳥でした。
詳しくはこちらのブログを
http://blog.goo.ne.jp/inpre-anac/e/9dda6d05da5a87e46bf2c6eaa51cba2e
見られた時間ちょうど近くにいたのに見られなかったので、とても悔しかったです。
その他に見られた珍鳥たちを紹介します。

オオチドリ
離島ではおなじみのオオチドリ

アカガシラサギ

コシャクシギ

ヒメコウテンシ
一度に200羽の群れが入っていたのには驚きました。

シロハラホオジロ

ノジコ
全般に、奄美群島では渡り鳥の多い年で、色々な珍鳥に出会えました。鳥屋にとってはとてもいい春の渡りでした。

2013年05月27日
アマミヤマシギの親子に遭遇
2012年06月28日
夜の林道
夜の林道に行ってきました。
今の時期、未舗装の林道を走ると今年生まれの幼鳥を連れたアマミヤマシギによく出会います。

アマミヤマシギ(幼鳥)
幼鳥(写真上)はよく見ると幼い顔つきで、足が黒っぽいです。親鳥(写真下)は子育て終えて換羽する時期になるので羽もぼろぼろで、脚は黒っぽくないです。

アマミヤマシギ(親鳥)

リュウキュウアカショウビン

オオトラツグミ
夜の林道を走るときは、道の上にいるアマミノクロウサギやカエルやヘビなどを注意してばかりいますが、時たま木の上に目をやるとリュウキュウアカショウビン(アカショウビンの亜種)や、オオトラツグミなど枝の上で眠っている姿にも出会えます。
マングース防除事業の成果で、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、アマミノクロウサギにも出会えるチャンスが増えてきているようで嬉しいことです。
まだまだ根絶に向けて頑張っていかなければならないので今後ともご理解ご協力よろしくお願いします。

今の時期、未舗装の林道を走ると今年生まれの幼鳥を連れたアマミヤマシギによく出会います。

アマミヤマシギ(幼鳥)
幼鳥(写真上)はよく見ると幼い顔つきで、足が黒っぽいです。親鳥(写真下)は子育て終えて換羽する時期になるので羽もぼろぼろで、脚は黒っぽくないです。

アマミヤマシギ(親鳥)

リュウキュウアカショウビン

オオトラツグミ
夜の林道を走るときは、道の上にいるアマミノクロウサギやカエルやヘビなどを注意してばかりいますが、時たま木の上に目をやるとリュウキュウアカショウビン(アカショウビンの亜種)や、オオトラツグミなど枝の上で眠っている姿にも出会えます。
マングース防除事業の成果で、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、アマミノクロウサギにも出会えるチャンスが増えてきているようで嬉しいことです。
まだまだ根絶に向けて頑張っていかなければならないので今後ともご理解ご協力よろしくお願いします。

2012年01月30日
奄美の冬鳥
今年は冬鳥の渡来が少なく、林道を走っていると、必ず目にしていたシロハラを見ない日もあるくらいです。
今年の年賀状に「本土では、珍鳥の情報はちらほらあるのに、普通の冬鳥が少ないようです。奄美ではどうでしょうか?」
という内容のメッセージが目立ったので、全国的に見ても冬鳥が少ないのでしょう。
どんな原因で少ないのかはわかりませんが、鳥が少ないのはさみしいです。
マングースにとって冬場の貴重なタンパク源となっているシロハラが少ない今年はマングースにとって餌の少ない厳しい冬になるはずです。
この冬は餌が少なくマングースの根絶に向けて捕獲しやすい年なので、チャンスを逃さず気合入れて頑張りますので応援よろしくお願いします。

2011年12月19日
冬の使者
北風が吹き、各地で冬の便りが聞かれるようになるとジョウビタキが渡ってきます。
ヒタキの仲間のジョウビタキは、庭先や、公園など、人の目に付きやすい場所で観察され可愛らしいので人気もあります。
オスは頭から背中にかけて銀白色で、お腹はオレンジ色、羽に大きな白斑があり、
メスは全身が褐色で、尾羽だけがオレンジ色、羽にある白斑はオスと同じです。
どちらも尾羽をピョコピョコさすのが特徴です。
オスの頭が銀白色なのがお爺さんの白髪に似ていることからお爺さんを意味する漢字、尉(ジョウ)鳴き声が火打石で、火を起こす時のような音「カカッ」「ヒッヒッ」なので、火焚き(ヒタキ)で、ジョウビタキになったと言われています。
支柱などの先に止まっていることが多く、虫を見つけては飛び降りて餌を捕まえています。
畑仕事中に気がつくと支柱に止まっているので、土を掘り返してやると餌を捕りにやって来るので、かわいいです。
ヒタキの仲間は目がクリクリで可愛いので、みなさんも見かけたらじっくり観察してみてください。