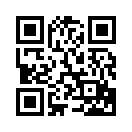マングースの目撃情報や、活動に関するお問い合わせは下記の連絡先にお願いいたします。
<一般財団法人自然環境研究センター 浦上事務所 鹿児島県奄美市名瀬浦上1385-2
TEL:0997-58-4013
環境省奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551TEL:0997-55-8620
このブログの写真の無断転載はご遠慮ください。写真については、一部を除いてメンバーが休日等利用して撮影したものを使用しています。2024年02月22日
世界初‼に挑んだ 奄美マングースバスターズの紹介動画が出来ました。
https://www.youtube.com/watch?v=OGJJqBQH04c&t=37s
不可能と言われた外来種根絶プロジェクトに挑んだ奄美マングースバスターズとは?
奄美の自然を守るプロ集団「奄美マングースバスターズ」。奄美大島からのマングース根絶を目標に2005年に結成されました。マングースを捕獲する高い技術、過酷な環境でも山を歩き通す体力、奄美の自然に対する知識、そして何より奄美大島の豊かな自然と生物多様性を愛し、マングースによって破壊された生態系をよみがえらせる熱意のもと集まったチームです。
幾多の困難を乗り越え、2018年のマングースの捕獲を最後に、約5年間にわたってマングースの生息は確認されておらず、いよいよ悲願の「奄美大島からのマングース根絶」が達成されるかもしれない状況です(2023年12月末日時点)。しかし、根絶達成を証明することは難しく、まだどこかにマングースが残っているかもしれません。また、沖縄などからの荷物に紛れて再侵入する可能性もあります。「もしかして、マングース?」と思う生き物を見かけたら下記の連絡先に目撃情報をお寄せください。
環境省 奄美野生生物保護センター TEL 0997-55-8620
奄美大島にマングースが放たれて30年、マングース防除事業に関わってきたすべての人達の熱意と努力を無駄にすることなくこれからも奄美の自然を見守り続けます。
不可能と言われた外来種根絶プロジェクトに挑んだ奄美マングースバスターズとは?
奄美の自然を守るプロ集団「奄美マングースバスターズ」。奄美大島からのマングース根絶を目標に2005年に結成されました。マングースを捕獲する高い技術、過酷な環境でも山を歩き通す体力、奄美の自然に対する知識、そして何より奄美大島の豊かな自然と生物多様性を愛し、マングースによって破壊された生態系をよみがえらせる熱意のもと集まったチームです。
幾多の困難を乗り越え、2018年のマングースの捕獲を最後に、約5年間にわたってマングースの生息は確認されておらず、いよいよ悲願の「奄美大島からのマングース根絶」が達成されるかもしれない状況です(2023年12月末日時点)。しかし、根絶達成を証明することは難しく、まだどこかにマングースが残っているかもしれません。また、沖縄などからの荷物に紛れて再侵入する可能性もあります。「もしかして、マングース?」と思う生き物を見かけたら下記の連絡先に目撃情報をお寄せください。
環境省 奄美野生生物保護センター TEL 0997-55-8620
奄美大島にマングースが放たれて30年、マングース防除事業に関わってきたすべての人達の熱意と努力を無駄にすることなくこれからも奄美の自然を見守り続けます。
2018年07月27日
職場体験を初めて受け入れ
奄美マングースバスターズとして初めて、中学生の職場体験を受け入れることになりました。さすがに山の中でのわな点検作業や探索犬の作業に同行、なんてことはさせられません。何してもらえば良い職場体験になるのだろうかと考えた末、1日目は安全な道沿いでのわな点検作業を、2日目は探索犬の仕事を説明して、地図とコンパスを使ったわな点検のシミュレーションをしてもらいました。

この職場体験では、生徒たちが興味のある職業の事業所に、直接連絡して依頼をするそうです。奄美マングースバスターズがどんな仕事をしているか知っていて、興味を持ってくれた子供たちがいることがうれしかったです。受け入れた生徒たちはみな奄美の自然や、自然保護に興味があり、将来奄美マングースバスターズで働きたいと言ってくれる生徒もいました。奄美野生生物保護センターの自然保護官になるのが夢だという生徒もいて、自分が中学生の時、将来なりたい職業ってなんだったかなと思い浮かべてみたら、なぜかカブトエビのエピソードを思い出しました。当時、自宅の前の田んぼだけにカブトエビがいて、まわりの田んぼにはいなかったので、まわりの田んぼでもカブトエビがとれるようになるといいなぁと思って、せっせと放流していたことがありました。今思えば意図的導入 で はありませんか!(ちなみに自宅の前の田んぼにはホウネンエビもいました。)生き物は好きでしたが、自然保護には興味はなく、ましてや固有種を保護しようという意識は全然ありませんでした。それに比べると、職場体験に来てくれた生徒たちは奄美の自然保護に関心を持って、こうして私たちのところを訪ねてくれました。そのことがすごいと思いました。

地図とコンパスの使い方では、中学校では習わない三角関数など駆使して地図上に磁北線を書いたり、理科で習う等圧線と等高線の共通点とを説明したりしました。本当に理解してくれたかどうかは謎ですが、学校の授業で習うことが、実際の仕事の中で役立つことがあるんだよという説明に、目を輝かせて聞いてくれました。

野外では自分の位置をコンパス使って確認したり、目的地への方向をコンパスで確認する方法などを体験してもらいました。
子供たちからの、「僕たちが大人になった時、奄美マングースバスターズに入れますか?」との問いに対して、「君たちが大人になった時にはマングースの根絶を達成しているはずなので、奄美マングースバスターズは解散していて…」と答えたら、ちょっと悲しい雰囲気になってしまったので、「マングースが根絶できても、奄美の自然を守る仕事は続くので、いろいろな勉強をして奄美大島に帰ってきてほしい」と伝えました。

奄美マングースバスターズには、奄美の子供たちを対象にした環境教育に力を入れていきたいという思いがあり、昨年から出前授業を行っています。今回2つの中学校から3名の職場体験の依頼があり、奄美の自然や自然保護に興味を持ってくれる子供たちが増えてきているのかなと思っています。これからも奄美の子供たちに自分の生まれ育った奄美大島の自然の豊かさを誇りに思ってもらえるよう、奄美の自然についての出前授業や職場体験の受入れを続けていきたいと思いました。
この職場体験では、生徒たちが興味のある職業の事業所に、直接連絡して依頼をするそうです。奄美マングースバスターズがどんな仕事をしているか知っていて、興味を持ってくれた子供たちがいることがうれしかったです。受け入れた生徒たちはみな奄美の自然や、自然保護に興味があり、将来奄美マングースバスターズで働きたいと言ってくれる生徒もいました。奄美野生生物保護センターの自然保護官になるのが夢だという生徒もいて、自分が中学生の時、将来なりたい職業ってなんだったかなと思い浮かべてみたら、なぜかカブトエビのエピソードを思い出しました。当時、自宅の前の田んぼだけにカブトエビがいて、まわりの田んぼにはいなかったので、まわりの田んぼでもカブトエビがとれるようになるといいなぁと思って、せっせと放流していたことがありました。今思えば意図的導入 で はありませんか!(ちなみに自宅の前の田んぼにはホウネンエビもいました。)生き物は好きでしたが、自然保護には興味はなく、ましてや固有種を保護しようという意識は全然ありませんでした。それに比べると、職場体験に来てくれた生徒たちは奄美の自然保護に関心を持って、こうして私たちのところを訪ねてくれました。そのことがすごいと思いました。
地図とコンパスの使い方では、中学校では習わない三角関数など駆使して地図上に磁北線を書いたり、理科で習う等圧線と等高線の共通点とを説明したりしました。本当に理解してくれたかどうかは謎ですが、学校の授業で習うことが、実際の仕事の中で役立つことがあるんだよという説明に、目を輝かせて聞いてくれました。
野外では自分の位置をコンパス使って確認したり、目的地への方向をコンパスで確認する方法などを体験してもらいました。
子供たちからの、「僕たちが大人になった時、奄美マングースバスターズに入れますか?」との問いに対して、「君たちが大人になった時にはマングースの根絶を達成しているはずなので、奄美マングースバスターズは解散していて…」と答えたら、ちょっと悲しい雰囲気になってしまったので、「マングースが根絶できても、奄美の自然を守る仕事は続くので、いろいろな勉強をして奄美大島に帰ってきてほしい」と伝えました。
奄美マングースバスターズには、奄美の子供たちを対象にした環境教育に力を入れていきたいという思いがあり、昨年から出前授業を行っています。今回2つの中学校から3名の職場体験の依頼があり、奄美の自然や自然保護に興味を持ってくれる子供たちが増えてきているのかなと思っています。これからも奄美の子供たちに自分の生まれ育った奄美大島の自然の豊かさを誇りに思ってもらえるよう、奄美の自然についての出前授業や職場体験の受入れを続けていきたいと思いました。
2018年05月25日
龍郷町立龍北中学校にてAMBの環境講話
龍郷町の龍北中学校から依頼をいただき、4月25日に全校生徒の皆さん12名に対して、環境講話として奄美大島の森の生態系と外来種をテーマに話をしました。
スライドと食物網の図を使って、奄美大島の主な森の生き物を紹介しつつ、マングースやネコが侵入したことで、森の食物網がどのように変わってしまったか、そして奄美マングースバスターズの仕事と成果について説明しました。
また、島の自然を守るために一人一人がどんなことをしたらよいかヒントになりそうなことについても触れました。
最後に、今日の話をどう感じたかアンケートを書いていただきました。時間が40分と限られていたので、話が駆け足になってしまいましたが、全員がよくわかった、まあまあ理解できたという感想でしたので、ホッとしました。
生徒たちの感想の中には、奄美マングースバスターズの存在は知っていたけど、実際にどんな仕事をしているのかを知らない子たちが多く、そのことだけでも伝えられたことは収穫でした。また、マングース以外の外来種(ヤギ・ノネコ・外来植物など)についても知らない生徒がいて、外来種が生態系に及ぼす影響についても伝えられたのはよかったと思います。
奄美マングースバスターズの出前授業は昨年に続いて2回目でした。今後も、若い人たちに島の自然や生き物にもっと関心を持っていただけるような機会を持ちたいと思います。
2017年06月23日
危険ポイント
雨の日が続き、やっと梅雨らしくなってきました。
ところで、マングースの探索作業中に歩きやすい尾根道を
マングース探索犬と歩いていると、
ちょっとした「ヒヤリハット」がありました。
さて、下の画像にはあるキケンが隠れています・・・。
おわかりでしょうか?

少し拡大して○で囲みました。

私は1.5メートルくらい手前で気が付き立ち止まりました(汗)。
もうおわかりですね。
ヒヤリハットした理由は、

ハブ!でした。
幸いにも攻撃体制ではないようでしたが・・、
みなさんも山を歩く際は気を付けてください。
ところで、マングースの探索作業中に歩きやすい尾根道を
マングース探索犬と歩いていると、
ちょっとした「ヒヤリハット」がありました。
さて、下の画像にはあるキケンが隠れています・・・。
おわかりでしょうか?

少し拡大して○で囲みました。

私は1.5メートルくらい手前で気が付き立ち止まりました(汗)。
もうおわかりですね。
ヒヤリハットした理由は、

ハブ!でした。
幸いにも攻撃体制ではないようでしたが・・、
みなさんも山を歩く際は気を付けてください。
2016年12月02日
新聞の取材を受けました。

糞探索犬のハンドラーと、糞探索犬
奄美マングースバスターズで、育成しているマングース探索犬について、取材を受けました。
奄美大島にはマングースを探す犬、マングース探索犬がいること、探索犬にはマングースそのものを専門に探す犬と、マングースの糞を専門に探す犬がいて、お互い仕事を分担し奄美大島からマングースの根絶を目指して頑張っているということ、根絶達成には探索犬は無くてはならない存在で、「根絶への切り札」ということを記者さんに伝えました。
今回は、朝日学生新聞社の取材でしたので、全国の子供たちに奄美大島のマングース探索犬や、奄美の自然について知ってもらえたら嬉しいです。
これをきっかけに多くの子供たちに奄美大島の自然を実際に見に来てほしいです。
糞を探しているところ
2015年08月15日
今年も救命救急講習に参加しました.

今日は名瀬消防署で救命救急講習がありました。私たち奄美マングースバスターズは毎年講習に参加させていただいております。今年は新人を中心に9名が参加させていただいきました。
講習は「119番通報してから救急車が到着するまで何分かかると思いますか?」という設問からはじまりました。
全国平均で8分だそうです。
その救急車が到着するまでの8分の間に救命処置をした場合と何もしなかった場合では、命が助かる可能性に大きな開きがあることが分かりました。
今回はこの救急車が到着するまでの救命処置の方法、心臓マッサージの仕方やAED(自動対外式除細動器)の使い方、人工呼吸の仕方などを教えていただきました。

奄美大島においても、この講習を受けた方が実際に救命処置を行い、命が救われた事例があるそうです。
講習を受ける前の私は、目の前に人が倒れていたら119番通報してただ動揺するだけだったに違いありません。
この講習を受けて救命処置やAEDが、命を救う上で大変重要であることが分かりました。
少しの勇気と行動で命を救うことが出来ることを学びました。
もし、必要な場面が訪れたら積極的に行動しようと思います。

2015年08月01日
住用小学校職場見学 (平成27年5月26日)
住用小学校の1・2年生の生徒さんたちが職場見学にいらっしゃいました。
生徒さんたちは普段聞く事ができない野生生物の話やマングースバスターズの仕事の話に興味津々でたくさんの質問をいただきました。

「なんでマングースを捕るんですか?」
「マングースは好きですか?」
「マングースは何を食べるんですか?」
「捕まえたマングースは殺しちゃうんですか?」

「ハブにあったときはどうしているんですか?」
「山の中ではどういうご飯をたべているんですか?」
「山の中に何人ではいるんですか?」
などなど・・・

無邪気で好奇心旺盛な質問に少し戸惑うこともありましたが、柔軟な発想にとても感心させられました。
最後に生徒さんたちに一番大事なことを伝えました。
「マングースはクロウサギを食べたりするけど本当は悪い動物ではありません。ハブを退治するために勝手に人間がもちこんだものです。マングースに何の罪もありません。」
そうなのです。奄美に生息しているフイリマングースの故郷はミャンマー、中国南部、バングラデシュ、ブータン、ネパール、インド、パキスタン、アフガニスタン、イランです。人間が勝手に連れてきてこの島に放したのです。それを今になって元の環境に戻そうと必死になって自分たちで持ち込んだマングースを駆除している。人間のエゴに翻弄されてきた奄美大島の生き物や、マングースは被害者なのです。
マングースの問題は奄美マングースバスターズに任せておいて、自分は無関係と思うのではなく、外来種に関心を持ってもらうだけで間接的に外来種対策に参加していることになるということと、奄美大島ではマングースの他にノネコの問題が課題になっているので、マングース防除事業の経験と反省を活かしてみんなで外来種対策やノネコの問題について考えていけたらいいなということも伝えました。
この後、生徒さんたちは次の職場見学へ。
素直で良い子たちでした。
たくさんいろんなことを吸収して立派な大人になってね(^_^)/~

P.S.後日このような素敵なものをいただきました。
ありがとう。大事にするよ(^o^)/。

生徒さんたちは普段聞く事ができない野生生物の話やマングースバスターズの仕事の話に興味津々でたくさんの質問をいただきました。
「なんでマングースを捕るんですか?」
「マングースは好きですか?」
「マングースは何を食べるんですか?」
「捕まえたマングースは殺しちゃうんですか?」

「ハブにあったときはどうしているんですか?」
「山の中ではどういうご飯をたべているんですか?」
「山の中に何人ではいるんですか?」
などなど・・・

無邪気で好奇心旺盛な質問に少し戸惑うこともありましたが、柔軟な発想にとても感心させられました。
最後に生徒さんたちに一番大事なことを伝えました。
「マングースはクロウサギを食べたりするけど本当は悪い動物ではありません。ハブを退治するために勝手に人間がもちこんだものです。マングースに何の罪もありません。」
そうなのです。奄美に生息しているフイリマングースの故郷はミャンマー、中国南部、バングラデシュ、ブータン、ネパール、インド、パキスタン、アフガニスタン、イランです。人間が勝手に連れてきてこの島に放したのです。それを今になって元の環境に戻そうと必死になって自分たちで持ち込んだマングースを駆除している。人間のエゴに翻弄されてきた奄美大島の生き物や、マングースは被害者なのです。
マングースの問題は奄美マングースバスターズに任せておいて、自分は無関係と思うのではなく、外来種に関心を持ってもらうだけで間接的に外来種対策に参加していることになるということと、奄美大島ではマングースの他にノネコの問題が課題になっているので、マングース防除事業の経験と反省を活かしてみんなで外来種対策やノネコの問題について考えていけたらいいなということも伝えました。
この後、生徒さんたちは次の職場見学へ。
素直で良い子たちでした。
たくさんいろんなことを吸収して立派な大人になってね(^_^)/~

P.S.後日このような素敵なものをいただきました。
ありがとう。大事にするよ(^o^)/。

2015年07月10日
全体ミーティングの様子
2014年12月12日
センサーカメラが捉えたコウモリとノネコ
奄美マングースバスターズではマングースを探知するため、森の中に1~2km2に一つの割合で自動撮影カメラ(センサーカメラ )を設置しています。

センサーカメラは熱を感知して作動するので、マングース以外の哺乳類や鳥類も撮影され、ときには思いがけない場面が撮れていることもあります。今回その中から2枚をご紹介します。

一枚目の写真に写っているのは、オーストンオオアカゲラをくわえたノネコです。
オーストンオオアカゲラは奄美大島だけに生息する国内希少野生動植物種です。国の天然記念物にも指定されている大型のキツツキで、ときどき地上の倒木を突いていることがあり、その姿がセンサーカメラに写っていることもあります。
ノネコとは「常時山野等において専ら野生生物を捕食し生活している」ネコのことで、 食物を残飯など人に依存しているノラネコとは違います。いま奄美の森ではマングースだけではなく、多くのノネコによっても日々たくさんの小動物が食べられているのです。

もう一枚の写真は、リュウキュウテングコウモリという奄美大島、徳之島、沖縄島の3島からのみ知られる固有種です。体長4~5cmほどの小さなコウモリで、樹洞がある太い木が生育している照葉樹林に生息しています。
これまでにも飛んでいるコウモリが写っていたことはときどきあり、その中には顔が写って種名がわかる場合もありましたが、どれもピンボケの写真ばかりでした。今回は偶然にも顔にかなりピントの合った写真が撮れました。テングコウモリの仲間の特徴的な鼻の形もはっきりわかります。
ちなみにこれまで名前がわかった写真はいずれもリュウキュウテングコウモリでした。カメラは1mほどの高さから斜め下に向けているので、この種はふだん森の中の低いところを飛び回っているようです。
どんな動物がどこでどのくらい写るかを分析することで、在来種の生息状況もわかります 。これまでの調査から、マングースが減ってきた事で、アマミノクロウサギやアマミトゲネズミの分布がしだいに回復し、拡大している事が解ってきました。
○参考文献:
動物愛護管理法例研究会編, 2006 動物愛護管理業務必携 大成出版社
鳥獣保護管理研究会編, 2008 改訂4版 鳥獣保護法の解説 大成出版社


センサーカメラは熱を感知して作動するので、マングース以外の哺乳類や鳥類も撮影され、ときには思いがけない場面が撮れていることもあります。今回その中から2枚をご紹介します。
一枚目の写真に写っているのは、オーストンオオアカゲラをくわえたノネコです。
オーストンオオアカゲラは奄美大島だけに生息する国内希少野生動植物種です。国の天然記念物にも指定されている大型のキツツキで、ときどき地上の倒木を突いていることがあり、その姿がセンサーカメラに写っていることもあります。
ノネコとは「常時山野等において専ら野生生物を捕食し生活している」ネコのことで、 食物を残飯など人に依存しているノラネコとは違います。いま奄美の森ではマングースだけではなく、多くのノネコによっても日々たくさんの小動物が食べられているのです。

もう一枚の写真は、リュウキュウテングコウモリという奄美大島、徳之島、沖縄島の3島からのみ知られる固有種です。体長4~5cmほどの小さなコウモリで、樹洞がある太い木が生育している照葉樹林に生息しています。
これまでにも飛んでいるコウモリが写っていたことはときどきあり、その中には顔が写って種名がわかる場合もありましたが、どれもピンボケの写真ばかりでした。今回は偶然にも顔にかなりピントの合った写真が撮れました。テングコウモリの仲間の特徴的な鼻の形もはっきりわかります。
ちなみにこれまで名前がわかった写真はいずれもリュウキュウテングコウモリでした。カメラは1mほどの高さから斜め下に向けているので、この種はふだん森の中の低いところを飛び回っているようです。
どんな動物がどこでどのくらい写るかを分析することで、在来種の生息状況もわかります 。これまでの調査から、マングースが減ってきた事で、アマミノクロウサギやアマミトゲネズミの分布がしだいに回復し、拡大している事が解ってきました。
○参考文献:
動物愛護管理法例研究会編, 2006 動物愛護管理業務必携 大成出版社
鳥獣保護管理研究会編, 2008 改訂4版 鳥獣保護法の解説 大成出版社

2013年12月09日
夏休みの宿題
早いもので今年もあと1か月きりましたが、夏の出来事を紹介します。
奄美マングースバスターズの事務所に小さなお客様がやってきてくれました。
夏休みも終わりの8月29日、奄美マングースバスターズの住用事務所を訪問してくれたのは、
住用小学校4年生の「牟田 蒼生(むた あおい)」君。

住用チームのリーダー。虫が専門ですが、奄美の生き物のことなら何でも教えてくれます。
夏休みの自由研究でアマミノクロウサギの事を調べていて、大和村にある環境省奄美野生生物保護センターで
「どうしてアマミノクロウサギの数が減ってしまったのか?」と質問したところ、
「マングースが食べてしまった事も影響している」と分かったので、マングースの事も調べてみようと思い、奄美マングースバスターズの住用事務所に調べにきてくれました。
マングースがどうしてアマミノクロウサギを食べているのか?
マングースバスターズの仕事内容は?
などの話の他にも、蒼生君は奄美の自然についてもたくさん話を聞いていました。
約30分程でしたが、しっかり話を聞いてノートにメモしていた蒼生君。
奄美の自然が好きだという事で、今までに調べた知識を披露してくれる場面もありました。
奄美大島にはいろいろな野生生物が生息しており、固有種も多く、調べれば調べるほど謎の多い島です。猛毒のハブが生息していることもあり、森の中での昆虫採集や、自然観察を子供だけではさせられないため、奄美の自然に興味を持ってくれる子供たちが少ないのではと心配しています。
毎日奄美の森に入って奄美の森を守り続けている我々奄美マングースバスターズは、奄美の自然に興味を持ってくれる子供たちの手助けになるよう頑張っていきたいです。また、こういった子供たちが増えてくれることも願っています。

話を聞いた後蒼生君は、「マングースの事がよく分かった」と言っていました。

奄美マングースバスターズの事務所に小さなお客様がやってきてくれました。
夏休みも終わりの8月29日、奄美マングースバスターズの住用事務所を訪問してくれたのは、
住用小学校4年生の「牟田 蒼生(むた あおい)」君。
住用チームのリーダー。虫が専門ですが、奄美の生き物のことなら何でも教えてくれます。
夏休みの自由研究でアマミノクロウサギの事を調べていて、大和村にある環境省奄美野生生物保護センターで
「どうしてアマミノクロウサギの数が減ってしまったのか?」と質問したところ、
「マングースが食べてしまった事も影響している」と分かったので、マングースの事も調べてみようと思い、奄美マングースバスターズの住用事務所に調べにきてくれました。
マングースがどうしてアマミノクロウサギを食べているのか?
マングースバスターズの仕事内容は?
などの話の他にも、蒼生君は奄美の自然についてもたくさん話を聞いていました。
約30分程でしたが、しっかり話を聞いてノートにメモしていた蒼生君。
奄美の自然が好きだという事で、今までに調べた知識を披露してくれる場面もありました。
奄美大島にはいろいろな野生生物が生息しており、固有種も多く、調べれば調べるほど謎の多い島です。猛毒のハブが生息していることもあり、森の中での昆虫採集や、自然観察を子供だけではさせられないため、奄美の自然に興味を持ってくれる子供たちが少ないのではと心配しています。
毎日奄美の森に入って奄美の森を守り続けている我々奄美マングースバスターズは、奄美の自然に興味を持ってくれる子供たちの手助けになるよう頑張っていきたいです。また、こういった子供たちが増えてくれることも願っています。
話を聞いた後蒼生君は、「マングースの事がよく分かった」と言っていました。

2013年11月29日
救急救命講習
最近ブログの更新が遅れていたので夏の記事になりますが、奄美マングースバスターズ全員で8月2日に名瀬消防署で普通救命講習を受講してきました。
講習の内容は家族や同僚などが万が一の時,救命の手助けができるコースとなっていて,心肺蘇生法と,AED(自動体外式除細動器)の使用法を学ぶ講習です。
心肺蘇生法は,強く,早く,絶え間なく行うことが重要で,呼吸をしていない場合は脳に血液が回らなくなり、命が助かった場合でも社会復帰するのが難しいということで,まずは胸骨圧迫による心肺蘇生が重要だということがわかりました。
AEDは止まった心臓を電気的なショックにより動かすものではなく、心室細動(心臓がけいれんしてるような状態)の状態でないと機械が作動しないようになっています。
AEDもできるだけ早期に使用し,AEDが作動する状態の場合は命が助かる確率も高いということがわかりました。
一通り講習を受けた後,様々な状況(若い女性の場合や,胸毛の濃い外人など)で,心肺蘇生法(胸骨圧迫)と,AEDの使い方をチェックするテストが行われましたが,バスターズメンバー全員合格して修了証をいただけました。
AEDによって一命をとりとめた方による
「私を救ってくれたのはAEDという機械だけではありません,見知らぬ私に駆け寄りAEDを使ってくれた勇気ある人々です」
という言葉が印象的でした。
胸骨圧迫や,AEDを使用するような状況は一生に1度あるかないかだとは思いますが,誰でも一人の命を救うことができるということと,講習内容を忘れないようにしたいです。

2013年08月16日
マダニの脅威
最近、世間を脅かしているマダニ!

ここ奄美大島でもたくさん生息しています。
マダニに一旦噛みつかれると、一週間以上体の表面から離れず、吸血し続け、ごく稀に感染症を引き起こすことがあるそうです。
我々奄美マングースバスターズは、マングース捕獲のために、日々山の奥に入りこみ、藪の中にも入っています。藪に入るたびに、ハブだけでなく、マダニにも気をつけて歩いていますが、かまれてしまいました。
足の太もも付近が何かもぞもぞするなと思っていたら、マダニがズボンの上からかみついていました。幸い皮膚に直接ではなかったもののがっつり噛まれてしまいました。

上の写真は噛まれた次の日の皮膚の状態です。非常に痒いです。しかし、我々奄美マングースバスターズは、そんなことにひるむことなく、マングース撲滅に向けて日々山中を駆けまわっています。 以上、現場のとある日の出来事でした。


ここ奄美大島でもたくさん生息しています。
マダニに一旦噛みつかれると、一週間以上体の表面から離れず、吸血し続け、ごく稀に感染症を引き起こすことがあるそうです。
我々奄美マングースバスターズは、マングース捕獲のために、日々山の奥に入りこみ、藪の中にも入っています。藪に入るたびに、ハブだけでなく、マダニにも気をつけて歩いていますが、かまれてしまいました。
足の太もも付近が何かもぞもぞするなと思っていたら、マダニがズボンの上からかみついていました。幸い皮膚に直接ではなかったもののがっつり噛まれてしまいました。

上の写真は噛まれた次の日の皮膚の状態です。非常に痒いです。しかし、我々奄美マングースバスターズは、そんなことにひるむことなく、マングース撲滅に向けて日々山中を駆けまわっています。 以上、現場のとある日の出来事でした。