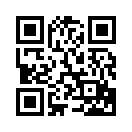マングースの目撃情報や、活動に関するお問い合わせは下記の連絡先にお願いいたします。
<一般財団法人自然環境研究センター 浦上事務所 鹿児島県奄美市名瀬浦上1385-2
TEL:0997-58-4013
環境省奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551TEL:0997-55-8620
このブログの写真の無断転載はご遠慮ください。写真については、一部を除いてメンバーが休日等利用して撮影したものを使用しています。2018年07月28日
ヤイロチョウ再び
奄美大島では通常、梅雨入りは5月の上旬、7月上旬に梅雨明けです。ジメジメした毎日が続いている奄美大島ですが、ちょっとしたうれしい出来事がありました。
マングースバスターズが、在来種とマングースのモニタリングのために設置しているセンサーカメラに、ヤイロチョウという鳥が再び撮影されました。
ヤイロチョウについては、奄美大島を渡り途中に通過はしているはずですが、姿が確認されず、長らく公式な記録がありませんでした。しかし、3年前にマングースバスターズの設置しているセンサーカメラで初めて撮影され、奄美野生生物保護センターの水田拓さんが「山階鳥類学雑誌」の「報告」に寄稿し、初めて公式に生息が確認されました。
ヤイロチョウ過去記事↓
今回は前回と違う場所で撮影されましたが、どちらも伐採等が長期間行われていない老齢林で、環境は似ています。撮影された時期は前回が5月中旬で、今回は5月下旬でした。



ヤイロチョウは全部で4枚撮影されていたのですが、4枚とも同じ日の撮影で、1枚目が10:00頃の撮影、4枚目が15:00頃の撮影でした。このヤイロチョウは、少なくとも1日は撮影された森の中にいただろうと想像できます。ヤイロチョウを奄美大島で目にすることがなかった原因として、島が大きくて森が深い、ということがあるかもしれませんが、島にいる期間が短いということもあるのではないかと思います。
こんなにカラフルなので、山の中でも目立つのかなと思いますが、人の気配を感じると忍者のように地面を歩いて姿を隠すので 意外と目立たないそうです。まさに幻の鳥ヤイロチョウ。奄美の森で見てみたいです。
梅雨時期の楽しみとして、来年の5月中旬から下旬には、ヤイロチョウに注意して山の中を歩いてみたいです。
マングースバスターズが、在来種とマングースのモニタリングのために設置しているセンサーカメラに、ヤイロチョウという鳥が再び撮影されました。
ヤイロチョウについては、奄美大島を渡り途中に通過はしているはずですが、姿が確認されず、長らく公式な記録がありませんでした。しかし、3年前にマングースバスターズの設置しているセンサーカメラで初めて撮影され、奄美野生生物保護センターの水田拓さんが「山階鳥類学雑誌」の「報告」に寄稿し、初めて公式に生息が確認されました。
ヤイロチョウ過去記事↓
今回は前回と違う場所で撮影されましたが、どちらも伐採等が長期間行われていない老齢林で、環境は似ています。撮影された時期は前回が5月中旬で、今回は5月下旬でした。
ヤイロチョウは全部で4枚撮影されていたのですが、4枚とも同じ日の撮影で、1枚目が10:00頃の撮影、4枚目が15:00頃の撮影でした。このヤイロチョウは、少なくとも1日は撮影された森の中にいただろうと想像できます。ヤイロチョウを奄美大島で目にすることがなかった原因として、島が大きくて森が深い、ということがあるかもしれませんが、島にいる期間が短いということもあるのではないかと思います。
こんなにカラフルなので、山の中でも目立つのかなと思いますが、人の気配を感じると忍者のように地面を歩いて姿を隠すので 意外と目立たないそうです。まさに幻の鳥ヤイロチョウ。奄美の森で見てみたいです。
梅雨時期の楽しみとして、来年の5月中旬から下旬には、ヤイロチョウに注意して山の中を歩いてみたいです。
2018年07月27日
職場体験を初めて受け入れ
奄美マングースバスターズとして初めて、中学生の職場体験を受け入れることになりました。さすがに山の中でのわな点検作業や探索犬の作業に同行、なんてことはさせられません。何してもらえば良い職場体験になるのだろうかと考えた末、1日目は安全な道沿いでのわな点検作業を、2日目は探索犬の仕事を説明して、地図とコンパスを使ったわな点検のシミュレーションをしてもらいました。

この職場体験では、生徒たちが興味のある職業の事業所に、直接連絡して依頼をするそうです。奄美マングースバスターズがどんな仕事をしているか知っていて、興味を持ってくれた子供たちがいることがうれしかったです。受け入れた生徒たちはみな奄美の自然や、自然保護に興味があり、将来奄美マングースバスターズで働きたいと言ってくれる生徒もいました。奄美野生生物保護センターの自然保護官になるのが夢だという生徒もいて、自分が中学生の時、将来なりたい職業ってなんだったかなと思い浮かべてみたら、なぜかカブトエビのエピソードを思い出しました。当時、自宅の前の田んぼだけにカブトエビがいて、まわりの田んぼにはいなかったので、まわりの田んぼでもカブトエビがとれるようになるといいなぁと思って、せっせと放流していたことがありました。今思えば意図的導入 で はありませんか!(ちなみに自宅の前の田んぼにはホウネンエビもいました。)生き物は好きでしたが、自然保護には興味はなく、ましてや固有種を保護しようという意識は全然ありませんでした。それに比べると、職場体験に来てくれた生徒たちは奄美の自然保護に関心を持って、こうして私たちのところを訪ねてくれました。そのことがすごいと思いました。

地図とコンパスの使い方では、中学校では習わない三角関数など駆使して地図上に磁北線を書いたり、理科で習う等圧線と等高線の共通点とを説明したりしました。本当に理解してくれたかどうかは謎ですが、学校の授業で習うことが、実際の仕事の中で役立つことがあるんだよという説明に、目を輝かせて聞いてくれました。

野外では自分の位置をコンパス使って確認したり、目的地への方向をコンパスで確認する方法などを体験してもらいました。
子供たちからの、「僕たちが大人になった時、奄美マングースバスターズに入れますか?」との問いに対して、「君たちが大人になった時にはマングースの根絶を達成しているはずなので、奄美マングースバスターズは解散していて…」と答えたら、ちょっと悲しい雰囲気になってしまったので、「マングースが根絶できても、奄美の自然を守る仕事は続くので、いろいろな勉強をして奄美大島に帰ってきてほしい」と伝えました。

奄美マングースバスターズには、奄美の子供たちを対象にした環境教育に力を入れていきたいという思いがあり、昨年から出前授業を行っています。今回2つの中学校から3名の職場体験の依頼があり、奄美の自然や自然保護に興味を持ってくれる子供たちが増えてきているのかなと思っています。これからも奄美の子供たちに自分の生まれ育った奄美大島の自然の豊かさを誇りに思ってもらえるよう、奄美の自然についての出前授業や職場体験の受入れを続けていきたいと思いました。
この職場体験では、生徒たちが興味のある職業の事業所に、直接連絡して依頼をするそうです。奄美マングースバスターズがどんな仕事をしているか知っていて、興味を持ってくれた子供たちがいることがうれしかったです。受け入れた生徒たちはみな奄美の自然や、自然保護に興味があり、将来奄美マングースバスターズで働きたいと言ってくれる生徒もいました。奄美野生生物保護センターの自然保護官になるのが夢だという生徒もいて、自分が中学生の時、将来なりたい職業ってなんだったかなと思い浮かべてみたら、なぜかカブトエビのエピソードを思い出しました。当時、自宅の前の田んぼだけにカブトエビがいて、まわりの田んぼにはいなかったので、まわりの田んぼでもカブトエビがとれるようになるといいなぁと思って、せっせと放流していたことがありました。今思えば意図的導入 で はありませんか!(ちなみに自宅の前の田んぼにはホウネンエビもいました。)生き物は好きでしたが、自然保護には興味はなく、ましてや固有種を保護しようという意識は全然ありませんでした。それに比べると、職場体験に来てくれた生徒たちは奄美の自然保護に関心を持って、こうして私たちのところを訪ねてくれました。そのことがすごいと思いました。
地図とコンパスの使い方では、中学校では習わない三角関数など駆使して地図上に磁北線を書いたり、理科で習う等圧線と等高線の共通点とを説明したりしました。本当に理解してくれたかどうかは謎ですが、学校の授業で習うことが、実際の仕事の中で役立つことがあるんだよという説明に、目を輝かせて聞いてくれました。
野外では自分の位置をコンパス使って確認したり、目的地への方向をコンパスで確認する方法などを体験してもらいました。
子供たちからの、「僕たちが大人になった時、奄美マングースバスターズに入れますか?」との問いに対して、「君たちが大人になった時にはマングースの根絶を達成しているはずなので、奄美マングースバスターズは解散していて…」と答えたら、ちょっと悲しい雰囲気になってしまったので、「マングースが根絶できても、奄美の自然を守る仕事は続くので、いろいろな勉強をして奄美大島に帰ってきてほしい」と伝えました。
奄美マングースバスターズには、奄美の子供たちを対象にした環境教育に力を入れていきたいという思いがあり、昨年から出前授業を行っています。今回2つの中学校から3名の職場体験の依頼があり、奄美の自然や自然保護に興味を持ってくれる子供たちが増えてきているのかなと思っています。これからも奄美の子供たちに自分の生まれ育った奄美大島の自然の豊かさを誇りに思ってもらえるよう、奄美の自然についての出前授業や職場体験の受入れを続けていきたいと思いました。
2018年07月26日
中央林道のムラサキカッコウアザミ駆除
4月27日に、奄美大島中央部に位置するきょらむん橋周辺で、外来植物であるムラサキカッコウアザミの駆除作業を行いました。

2015年から始めた駆除作業も今年で4回目となりました。
過去の経緯はこちらをご覧ください↓
当初はびっしりと繁茂していたのですが、生えている場所が狭まり、駆除作業を続けてきた成果が出てきました。
まだ完全には駆除できてはないのですが、ところどころ在来の草が生えてきて、外来種がはびこっているという状況からは脱出できたと感じています。
年に一回だけの作業にもかかわらず、ムラサキカッコウアザミの駆除作業を継続することで、繁茂するスピードを遅らせることが出来ています。

今回は、残っている小さなムラサキカッコウアザミ群落を除去する作業を集中して行いました。駆除作業を進めると、意外に多くの群落が残っていることがわかり、手を抜くことなく継続して駆除しなければ密生状態に戻ってしまうな、と感じました。特に花が咲いていない株は見逃され易く、作業が終わった場所をもう一度よく見てみると、抜き残しが結構ありました。次回はもう少し人数を投入し、抜き残しを出さないよう、徹底した駆除作業を行いたいと思います。

奄美マングースバスターズ13名、環境省3名 ゴミ袋15袋分駆除(約70kg)の駆除できました。
※ムラサキカッコウアザミ 熱帯アメリカ原産のキク科の多年草。環境省及び農水省の「生態系被害防止外来種リスト」では、ギンネムやタチアワユキセンダングサ等とともに総合対策外来種に選定されている。
2015年から始めた駆除作業も今年で4回目となりました。
過去の経緯はこちらをご覧ください↓
当初はびっしりと繁茂していたのですが、生えている場所が狭まり、駆除作業を続けてきた成果が出てきました。
まだ完全には駆除できてはないのですが、ところどころ在来の草が生えてきて、外来種がはびこっているという状況からは脱出できたと感じています。
年に一回だけの作業にもかかわらず、ムラサキカッコウアザミの駆除作業を継続することで、繁茂するスピードを遅らせることが出来ています。
今回は、残っている小さなムラサキカッコウアザミ群落を除去する作業を集中して行いました。駆除作業を進めると、意外に多くの群落が残っていることがわかり、手を抜くことなく継続して駆除しなければ密生状態に戻ってしまうな、と感じました。特に花が咲いていない株は見逃され易く、作業が終わった場所をもう一度よく見てみると、抜き残しが結構ありました。次回はもう少し人数を投入し、抜き残しを出さないよう、徹底した駆除作業を行いたいと思います。

奄美マングースバスターズ13名、環境省3名 ゴミ袋15袋分駆除(約70kg)の駆除できました。
※ムラサキカッコウアザミ 熱帯アメリカ原産のキク科の多年草。環境省及び農水省の「生態系被害防止外来種リスト」では、ギンネムやタチアワユキセンダングサ等とともに総合対策外来種に選定されている。