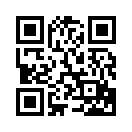マングースの目撃情報や、活動に関するお問い合わせは下記の連絡先にお願いいたします。
<一般財団法人自然環境研究センター 浦上事務所 鹿児島県奄美市名瀬浦上1385-2
TEL:0997-58-4013
環境省奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551TEL:0997-55-8620
このブログの写真の無断転載はご遠慮ください。写真については、一部を除いてメンバーが休日等利用して撮影したものを使用しています。2015年07月02日
奄美マングースバスターズ結成10周年メッセージその1

2005年、外来生物法が施行され奄美大島マングース防除事業が開始しました。同時に奄美マングースバスターズが結成され、7月1日で10年の節目を迎えることになりました。
2005年12名でスタートした奄美マングースバスターズ。数々の困難をチーム一丸となって乗り越えてきました。現在は探索犬もメンバーに加わり44名と9頭の探索犬で奄美の森を守るため日々活動しております。
2005年度には約2600頭ものマングースを捕獲していたのが2014年度はワナで33頭、探索犬による捕獲が32頭と根絶まであと一歩のところまで来ています。2015年度6月30日現在マングースの捕獲はワナで3頭、探索犬による捕獲は8頭(暫定)にまで減少し、近い将来ワナでの捕獲数ゼロも夢ではなくなってきています。まさに奄美マングースバスターズ「10執念」(しゅうねん)のたまものです。
1979年に奄美大島にマングースが持ち込まれてから36年、バスターズだけではなく多くの方々がマングース防除事業にかかわってこられました。
マングース防除事業にかかわってこられた方からマングースバスターズ結成10周年という事でメッセージを頂いていますので4回にわたり紹介いたします。
奄美大島フイリマングース防除事業検討委員からのメッセージ
7月1日で10周年ですか。おめでとうございます。私の頭の中では2007年から、がらっと奄美のマングース低密度化(意味のある)が実現しているので、AMBの業績は速攻であがっていたわけです。その後は、前人未到のこの大きさの島からの根絶作業ですから、今が辛抱どきです。これもはっきりいって、安易に根絶できる、とは言いたくないし、言えません。でも、これは言える。「できるのは、AMBしかいない。」あと、関係ないかもしれませんが、私の地元浦和レッズが前期はとりあえず無敗で優勝しました。このまま、後期も含めて無敗で行ってほしい。ん、なんか今年は験がよい気もする。今年根絶確認はないまでも、何か新たに、よい進展がありそうです。フレー、フレー、AMB。
奄美大島フイリマングース防除事業検討委員
東京大学大学院農学生命科学研究科准教授 石田 健

10周年おめでとうございます。以下のメッセージをお送りします。
猛暑や降雨、険しい地形でのいつもの現場作業に加え、常に技術を改善しようとチームで議論しているバスターズの姿が印象的です。マングース対策の10年間の技術の蓄積が、近年のマングースの極低密度化とアマミノクロウサギなど奄美の貴重な生物の回復につながったのだと思います。日本だけでなく、世界の関係者が、現在の奄美の取り組みに注目しています。これからマングース根絶に向けての最後の正念場をむかえます。これまでどおりチーム力をいかんなく発揮して、マングースの根絶、そして奄美大島のいきものたちが生き生きと暮らせる森が取り戻されることを期待しています。
奄美大島フイリマングース防除事業検討委員
独立行政法人森林総合研究所
亘 悠哉
マングースを712km2という大きさをもつ奄美大島から根絶することは、従来の世界の常識から考えると、とても信じられないことでした。
しかし、これまで奄美マングースバスターズは、数々の困難を日々の努力とアイディアによって乗り越え、外来生物との戦いの歴史に新たな1ペー ジを刻もうと しているように見えます。これから根絶達成に向けては様々な苦労があると思います。
そう遠くないうちに、年間のマングース捕獲数が0という時期が訪れるでしょう。そこから根絶達成までモチベーションを維持し続けるには強い精神力が必要で、そこが外来生物根絶の正念場です。やりがいを持って根絶達成の日まで仕事ができるよう、みなさんと知恵を絞りたいと思います。
世界に目を向ければ、そこにはまだ外来生物の被害に苦しむ現場がたくさんあります。
マングース根絶達成の暁には、そのような場所を「第2、第3の奄美」に変えていくことが、バスターズの皆さんの新たな使命になるかもしれません。世界のトップを走っているという自負を持って、これからもマングース根絶に向けてまい進していきましょう。
奄美大島フイリマングース防除事業検討委員
独立行政法人国立環境研究所研究員 深澤圭太